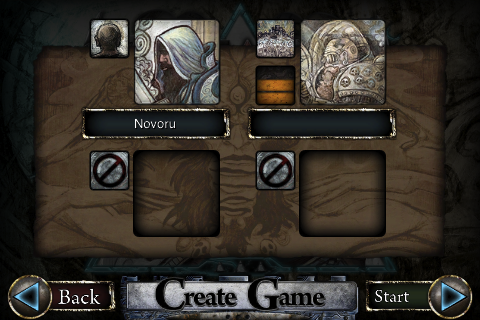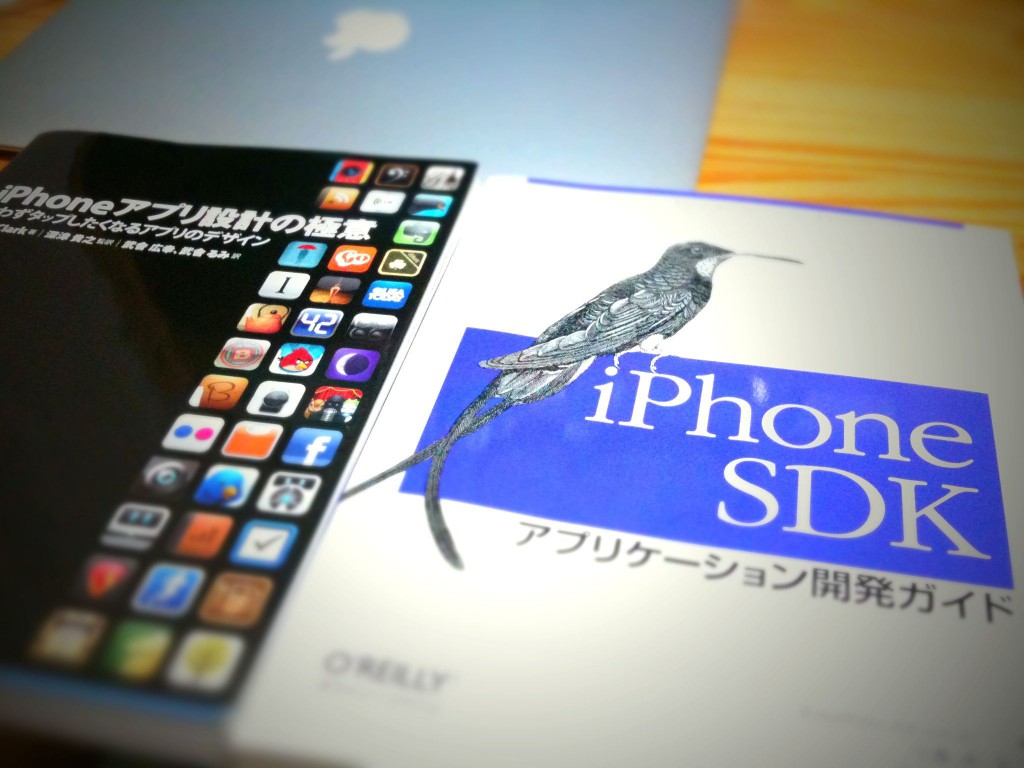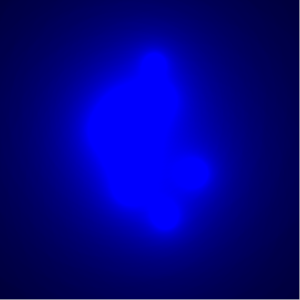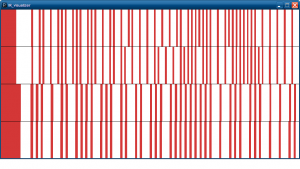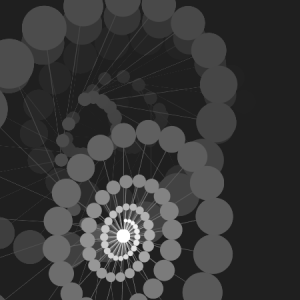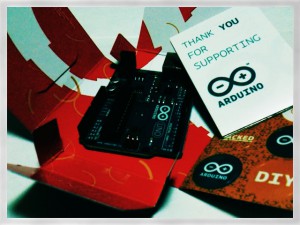相も変わらずAscensionに興じる日々。
現時点での実力はCPUレベル2と対戦して勝率五分くらい。
ドロー系のカードをつなげてコンボを決める楽しさがようやく分かってきた。
デッキ内のRune、Power収集効率のバランスを考えるのが楽しい&難しい。
基本的にはドロー系のカードとConstructs回収をメイン戦略に据えつつ、手札によって引くカードを変えていく、というざっくりとした戦略でやってます。
あとこのゲームやってて、一つ気になってることがある。
それはCPUレベルに3があるのかどうか。
上の写真右上のCPUアイコン脇についてるバーがCPUレベルを示している。
これ、明らかに3段階までいきそうな感じがするんだけど、どうタッチしても写真の状態にしかならない。
プレイしてくうちにアンロックされるとかなのかしら?